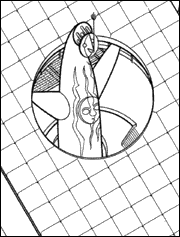
昭和45年、万博のシンボル「太陽の塔」
+
+
テクニック&ポイント
大阪万博の図は、ボルマン図法で制作。図面や写真、スケッチなどをもとに、平面地図に1対1のスケールで建物を垂直に立ち上げている。ボルマン(ドイツ人)は、都市を厳密な等測投影図法で描き、とくにニューヨークの絵地図が有名である。
|
|
忘れられない充実感があった
+
+
1970年に開催された大阪万博の公式ガイドマップ。森下さんは主にスクライブ(線版彫刻)を手がけた。作業は約4カ月の間、ほぼ軟禁状態で続けられたという。およそ6500万人の人々が見物に訪れ、華やかな会場で手にしたマップには、実はたくさんの制作者たちのエネルギーが注ぎ込まれていた。ちなみに、この博覧会のテーマは「人類の進歩と調和」だ。
地図は、建物や街が完成してから作るのが通常のプロセスです。ところが、大阪万博のときは、会場の工事と同時進行で地図を作らなければなりませんでした。資料となる図面の量は膨大で、1トン積みトラック数台分になったと記憶しています。私が作図した直径2ミリのロープウエイのゴンドラでさえ、B全判5枚の量になりました。
先輩諸氏がパビリオンごとに作図したものを印刷用図面にまとめるためには、一人の技術者が同じタッチで仕上げなければなりません。その大役を命じられたのが私です。作業は、3坪ばかりの小部屋に半ば軟禁状態で約4カ月、彫刻針を持つ手の中指にペンだこができ、それが破れて血を流しながらやりました。出入り口が2度も設計変更になったり、工事が間に合わず屋根がフラットになったパビリオンもありました。
作業中は「もうこんな仕事は二度とやらないぞ」と思いながら、しかし、出来上がってしまうと楽しさだけが残っていました。
最近はマックで仕事をしていますが、どんなに頑張ってもスクライブの味のある線は描けません。デジタルで制作されたものは、あまりにも線がシャープで冷たいのです。たしかに制作費は廉価で済みますし、何度やり直しても線が崩れることがありません。どんな修正も簡単です。しかし、残念なことに「やった!」という充実感はわきません。
構成 三代川律子[フリーライター]
+
+
|